
【熱帯魚の薬浴】失敗しない!薬浴のやり方&戻し方



7分

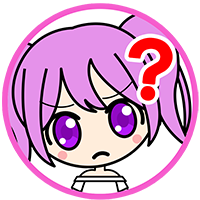
ん!?なんか熱帯魚の体表に茶色い点々付いてない!?
熱帯魚の体表に小さなキスゴムのような茶色い点が見られる『ウオジラミ(チョウ)症』。
寄生されると熱帯魚はかゆみを感じて体を擦り付けるようになり、そのまま放っておくと最悪死に至る事もあります。
この記事ではウオジラミ症の症状や治療法、予防法などを解説します。
ウオジラミ症になってしまったら茶色い点をピンセットで取って、それから薬浴が効果的です。
ウオジラミ症は早期発見、早期治療すれば完治する可能性も高いので、熱帯魚の健康を守るために、ぜひ参考にしてください。
それではいってみましょう。
ウオジラミ症は熱帯魚の体の表面にとても小さなキスゴムのような茶色い点が見られる病気です。
体表に付着している茶色い点はウオジラミと呼ばれる外部寄生虫。
ウオジラミは熱帯魚の体表に付着し、針を突き刺して魚の血液を吸います。
ウオジラミ症になったからと言って、すぐ魚が死んでしまう事はありませんが、治療せずに放っておくと死に至る怖い病気です。

熱帯魚がウオジラミ症になってしまった場合、どうなるのか具体的な症状を見ていきましょう。
熱帯魚の体の表面に数箇所の茶色い点が見られます。
点の色は半透明だったり、淡い青色に見える場合もあります。
5mm程度のものなので、観察すれば肉眼でも確認できると思います。
この茶色い点はよく観察していると動きます。
熱帯魚が突然飛び跳ねたり、急に方向転換したり、ヒレを震わせたり、いろんなところに体を擦り付けたり変な行動をします。
熱帯魚の体全体に点が見られます。
大量に寄生されてしまうと過度のストレスにより弱っていき、最終的に熱帯魚は衰弱死・失血死します。
ウオジラミ症は特に大型の熱帯魚が発症する事が多い病気です。
ウオジラミ症で熱帯魚がすぐに死に至る事はありません。
しかし、症状が進行すると死に至る事もありますし、寄生された傷口から細菌やカビの二次感染の場になります。

進行すると衰弱死の危険性があり、二次感染の恐れもある為、ウオジラミ症は早期発見・早期治療が重要です。
まず、体表に寄生しているウオジラミをピンセットで取ってください。
簡単に取れますが、取るときは熱帯魚の体を傷つけないようにそっと慎重に行ってください。
ウオジラミを除去しても、寄生されたところから高確率で細菌感染症を起こしますし、水槽内には卵や幼生が大量に存在しているので、薬浴による治療が必要になります。
使用する薬ですが、鑑賞魚専用の寄生虫駆除薬ムシクリア液がおすすめです。
レスバーミンやデミリンなども効果的ですが、専用の薬ではありません。
水槽内には卵や幼生が大量にいる為、隔離はせず水槽にムシクリア液を規定量入れてください。
治療期間ですが、だいたい1ケ月ぐらいを目安に薬浴を行ってください。
2週間程度で薬の効果が切れるので、3回ぐらい繰り返し薬を投入してください。
塩浴を併用すると魚の自然治癒力の後押しが期待出来ます。
水温が低いとウオジラミの成長が遅くなり、長期間の薬浴が必要になるので、水温は26~28℃くらいで行うようにしてください。

ピンセットで取る時は慎重にね!!治療はムシクリア液で1ケ月薬浴だよ!!

ウオジラミ症の原因はウオジラミ(アルグルス・ヤボニクス)と呼ばれる外部寄生虫に寄生された為です。
ウオジラミは薄い円盤状の甲殻類で、熱帯魚の体表や各ヒレに寄生し、鋭い口で、血を吸います。
さらに毒液注入により、強い炎症がおこり出血します。
血を吸われる上に、ウオジラミが増えて、どんどん寄生するので魚は衰弱してしまいます。
ウオジラミは遊泳能力も持っている為、3~5日宿主から離れても生きていけます。
ウオジラミですが、自然発生する事はなく、原因はほぼ100%外部からの持ち込みによるものです。
大型魚や古代魚の餌の小赤や導入した魚によって水槽に持ち込まれる事が多いです。
ウオジラミは魚の追加や新規導入など外部からの持ち込みによるものです。
つまり、水槽に外部から魚を追加する時に対策をすれば予防する事ができます。
その為、魚の導入時はトリートメントと呼ばれる作業をするようにしましょう。
ここでは割愛しますが、トリートメントの方法については別の記事で詳しく紹介していますので、読んでみてください。
トリートメントをすれば、ウオジラミ症やイカリムシ症といった病気はある程度予防できますので、少し面倒かもしれませんが魚の健康も考えて行うようにしましょう。

10%程度の塩浴で駆除は出来るかもしれませんが、魚も死んでしまいます。その為、塩だけでの駆除はおすすめしません。
薬を使うと駆除する事ができます。ムシクリア液が鑑賞魚専用でイカリムシやウオジラミ用の薬なのでおすすめです。
新しく魚を導入した時のウオジラミが寄生していて、水槽に持ち込まれた事が原因です。
ウオジラミはイカリムシと同様、肉眼でも確認できるので分かりやすいと思います。
治療法もイカリムシとほぼ一緒ですが、ウオジラミの場合は進行し、全身に寄生すると衰弱死や失血死を引き起こします。
その為、イカリムシ症よりも厄介な病気でもあります。
治療する時はまずピンセットでウオジラミを取ってから、薬浴を行うようにしてください。
使う魚病薬はムシクリア液がおすすめです。
とにかくウオジラミを持ち込ませないように予防する事がとても大切です。
少し面倒でも新しい魚を水槽に導入する場合はトリートメントを行うようにしましょう。